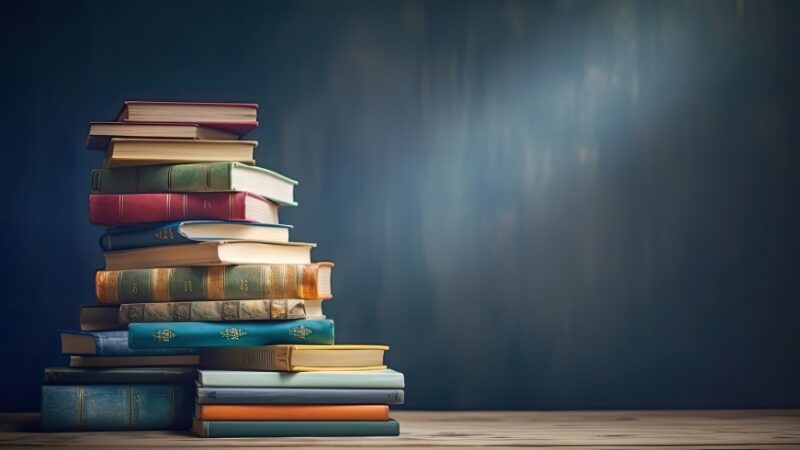
読書は知識が広がり、想像力が豊かになる趣味です。しかし、本の種類が多いため、多くの人がどの本を選べばいいか悩んでいます。この記事では、本の種類や分類方法、自分に合った本の選び方について解説します。記事を読めば、本について深く理解でき、自分にぴったりな1冊との出会いが可能です。
本には文芸や実用書、ビジネス書などさまざまな種類があり、サイズや製本方法も異なります。自分の興味や目的に合わせて本を選ぶと、読書がより楽しくなります。
本の種類を理解する重要性

本の種類への理解は、豊かな読書をするうえで重要です。適切な本を選ぶと、学習が効率的になります。目的や興味に合った本を選ぶと、より多くの情報を得られる点もメリットです。書店や図書館での本の探し方がわかると、充実した読書ができるうえ、読書習慣も身に付きます。
本の種類

本の種類は、以下のとおりです。
- 文芸
- 実用書
- ビジネス書
- 絵本・児童書
- 学習参考書
- 専門書
- コミック・雑誌
種類ごとの特徴を理解すると、自分の目的や興味に合った本を選びやすくなり、読書の幅が広がります。読書を通じて新しい知識や楽しみも得られます。
» 本の大まかなジャンル分け&タイプ別おすすめジャンル
文芸
文芸は、小説や詩集、エッセイ、短編集、戯曲、評論など、幅広いジャンルを含む文学作品の総称です。以下のようなジャンルがあります。
- ミステリー
- ファンタジー
- SF
- ホラー
- ロマンス
- 歴史小説
- 青春小説
文芸作品は読者の感性や想像力を刺激し、心に深い印象を与えます。古典文学から現代文学まで時代を超えて愛され、海外文学の翻訳作品も豊富です。文学賞受賞作は特に評価が高く、注目されます。文学的価値や社会的影響力が認められた作品は、読書の幅を広げるきっかけになります。
文芸作品を読むと、新たな視点や考え方に触れられ、豊かな感性の会得が可能です。言葉の美しさや表現力も学べます。
実用書
実用書は、日常生活や特定のスキルに役立つ情報を提供する本です。料理やDIY、ガーデニングなど、実践的なトピックを扱います。ハウツーや手順の解説がメインで、図解や写真が多い点が特徴です。専門家や経験者が書いているため、問題解決や目標達成に役立ちます。
実用書は、生活に役立つ情報が学べ、多くの読者に支持されています。順序立てた説明が多く、初心者でも理解しやすい点がメリットです。定期的に改訂版が出版される本も多く、最新の情報を得られます。実用書を読むと、新しいスキルを身に付けたり、日常生活を豊かにしたりできます。
ビジネス書

ビジネス書は、実務的なスキルや知識を学ぶための本です。主にビジネスマン向けの内容が中心となっています。リーダーシップやマネジメントに関する知識、戦略立案などのビジネススキルなどが学べます。成功事例や経営者の体験談、自己啓発や時間管理に関する内容も特徴です。
ビジネス書には、図表やチャートが多く掲載され、視覚的にわかりやすくなっています。ケーススタディや演習問題が載っているビジネス書の場合、実践的な学びが得られます。最新のビジネストレンドや技術に関する情報も多く、変化するビジネス環境を学ぶうえでも効果的です。
ビジネス界で成功した人物や専門家が書いているビジネス書が多くあります。ビジネス書は、読者の行動を促すのが目的です。ビジネスシーンで活用できる知識やスキルを身に付けられるため、キャリアアップを目指す人に向いています。
絵本・児童書
絵本・児童書は、子どもの成長と学びを支える大切な読み物です。幼児から小学生まで、幅広い年齢層の子どもたちに向けて作られています。主な種類は、以下のとおりです。
- 物語絵本
- 知育絵本
- しかけ絵本
- 図鑑
- 童話
- 学習漫画
絵本・児童書は、豊富なイラストや写真、大きな文字が特徴です。教育的要素や想像力を育む内容で、年齢別の難易度になっています。物語や知育、学習など、さまざまなジャンルも特徴です。子どもたちは楽しみながら学べます。親子で一緒に読む場合も多いため、コミュニケーションにも効果的です。
絵本・児童書は、子どもの興味や発達段階に合わせて選べます。図書館や学校でも利用されており、子どもたちにとっても身近な存在です。最近では、デジタル版や電子書籍の絵本・児童書も増えています。
学習参考書

学習参考書は、学習者の理解を深め、知識を広げるための本です。教科書の内容を補完し、効果的な学習をサポートします。学習参考書の種類は、以下のとおりです。
- 教科書の補助教材
- 問題集や演習帳
- 受験対策用の参考書
- 資格試験対策の教材
- 学習ガイドや解説書
学習参考書は、レベルや目的に合わせて選びましょう。基礎固めには問題集や演習帳が適しています。受験を控えている場合、受験対策用の参考書が有効です。学習参考書を上手に使うと、学習効率が上がり、理解も深まります。自分に合った参考書を見つけ、計画的に学習を進めましょう。
専門書
専門書は、特定分野の専門的な知識や技術を扱う本です。一般の読者向けの本とは異なり、専門家や研究者を対象としています。学術的・専門的な内容が多く、専門用語や技術的な説明が書かれています。最近の研究成果や理論、図表やデータが多く含まれる点が特徴です。
専門書は、特定の業界や学問分野に特化しているため、特化した分野の知識を深めたい人に役立ちます。一般の人には難解な場合がある点に注意してください。専門書は一般の本より価格が高く、発行部数も比較的少なめです。大学や研究機関の図書館でよく利用されています。
コミック・雑誌
コミックは物語を絵と文字で表現した本で、雑誌は定期的に発行される冊子形式の出版物です。娯楽や情報を提供します。マンガ単行本やコミックス、グラフィックノベルなどの形態、週刊誌や月刊誌、季刊誌などの発行頻度での分類が可能です。ジャンルは少年向けや少女向け、青年向け、成人向けなどがあります。
最近はデジタルコミックや電子雑誌も増え、手軽に多くの作品を楽しめるのが特徴です。同人誌やウェブコミックなど新しい形態も登場し、芸術性の高いコミックや専門的な雑誌も出版されています。コレクターズアイテムとして価値が高い本もあります。
本のサイズの種類
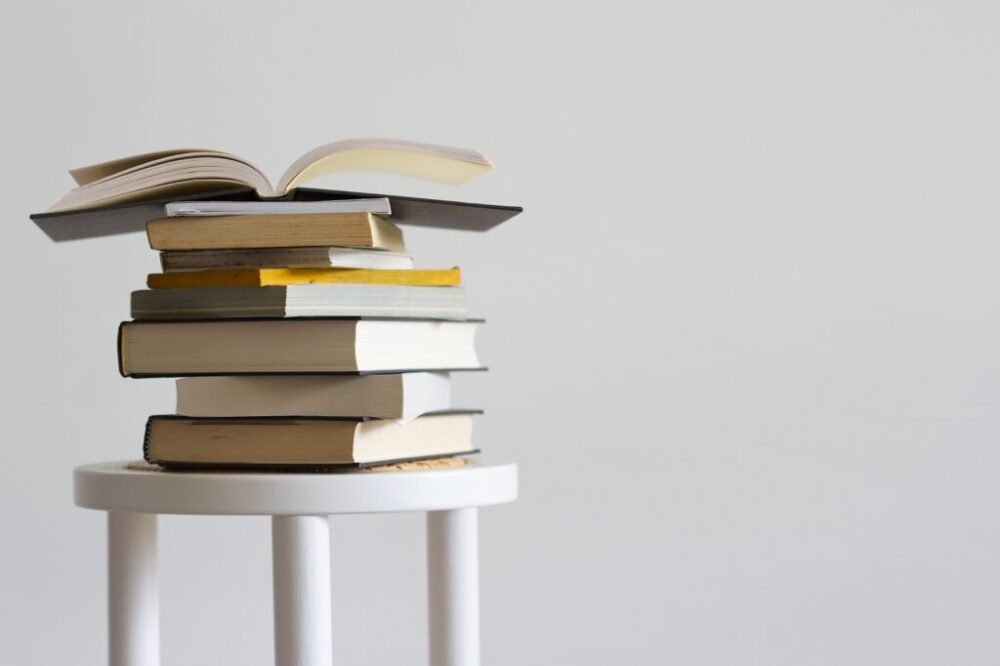
本のサイズの種類は、以下のとおりです。
- 文庫本
- 新書
- 単行本
サイズによって読みやすさや持ち運びやすさが変わるため、自分の好みや目的に合わせて選びましょう。
» 本の一般的なサイズから特殊なサイズまでを解説!
文庫本
文庫本は一般的にA6サイズで、携帯性に優れています。価格が比較的安く、購入しやすい点が特徴です。軽くて持ち運びやすく、電車内や寝る前の読書に適しています。コレクションしやすい点も魅力です。多くの文庫本は、単行本の廉価版として発行されます。
人気の高い文学作品やエンターテインメント小説が文庫化される傾向です。ペーパーバック形式で製本されるため耐久性は低くなりますが、手軽で安く、多くの読者に愛されています。文庫本は日本の出版文化の特徴です。「文庫文化」と呼ばれるほど根付いています。
再販売制度の対象になっているため、定価での販売が一般的です。読書の習慣づけや、さまざまなジャンルの本の試し読みに向いています。
» 文庫本のサイズはどれくらい?他の書籍との違いも解説!
新書
新書はA5サイズの小型本で、手軽に読める点が特徴です。価格が安く、持ち運びにも便利で、若年層に人気があります。新書の魅力は、学術的な内容を専門的かつ簡潔に解説する点です。新しい知識や情報が書かれ、最新のトピックを扱う場合が多いため、速報性が高くなります。
文庫本より少し大きめで、入門書に適しています。岩波新書や講談社現代新書などが有名です。新書は、特定の分野を学びたい人におすすめです。文庫化される前の段階で出版される場合もあるため、最新情報の収集に適しています。
単行本
単行本は、標準的な大きさの書籍です。ハードカバーで製本され、A5判やB6判が一般的です。新刊の多くが単行本として出版されます。特徴は、以下のとおりです。
- 文庫本や新書より高価になる
- 耐久性が高くなる
- 保存性に優れている
- デザイン性が高くなる
- フトに適している
単行本は専門書や写真集でよく使用され、本棚に並べやすく、読みやすさと携帯性のバランスに優れています。200〜400ページ程度が一般的です。造りがしっかりしており、サイズ感が適度なため、じっくりと読み込みたい本や、長く手元に置きたい本に向いています。
» 文庫本と単行本の違いは?自分の読書スタイルに合う本の選び方
本の製本の種類
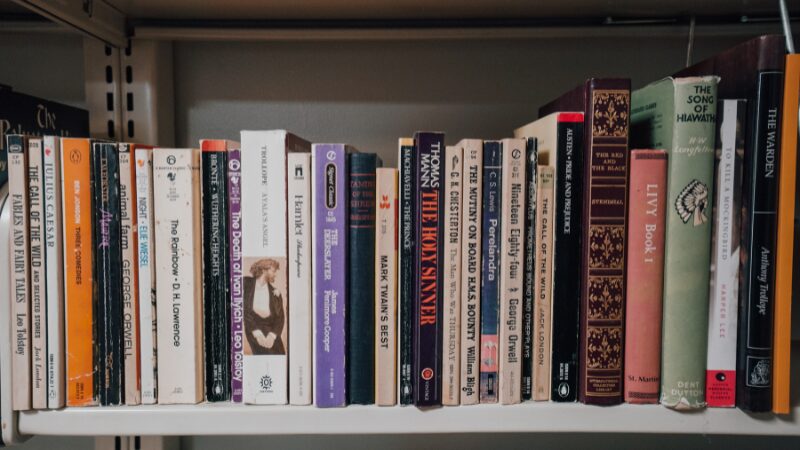
本は製本の方法によって耐久性や見た目、価格が変わります。製本の種類は、以下のとおりです。
- 上製本
- 並製本
- クレスト装
上製本
上製本は、高品質な製本方法です。耐久性が高く、長期保存に適しています。表紙には厚紙を使用し、布や皮で装丁します。丸みを帯びた背表紙や糸かがりの製本、開きやすい点も特徴です。高級感があり、贈答用や保存用に適しています。
単行本やハードカバーの書籍で使用され、図書館の蔵書や美術書、写真集などでよく見かけます。製作コストがかかるため、価格は比較的高めです。本文用紙の端を金や銀でコーティング加工する場合もあり、高級感が増します。
並製本
並製本は、一般的な単行本や文庫本で多く採用されている製本方法です。表紙が柔らかい紙やカバーで覆われており、のりで背表紙を接着します。特徴は、以下のとおりです。
- 比較的安価
- 軽量
- 製作コストが低め
- リサイクル向き
上製本に比べると耐久性は劣りますが、本が薄い場合や、短期間で使用する場合に適しています。並製本は長期保存には向いていないため、用途に応じて選びましょう。
クレスト装
クレスト装は、並製本の一種で、耐久性が高く比較的安価な製本方法です。表紙には厚紙が使用され、光沢のある加工が施されています。表紙にクレスト加工(エンボス加工)が施され、表紙の角が丸い点が特徴です。背表紙が平らで、本を立てて置けます。開きやすく、読みやすい点もメリットです。
クレスト装は、学習参考書や実用書によく使用されます。丈夫な装丁で長期間の使用に耐えられるため、繰り返し読む本に最適です。比較的安い場合が多く、幅広い読者に人気があります。多くの出版物で採用されている製本方法です。
本の分類方法
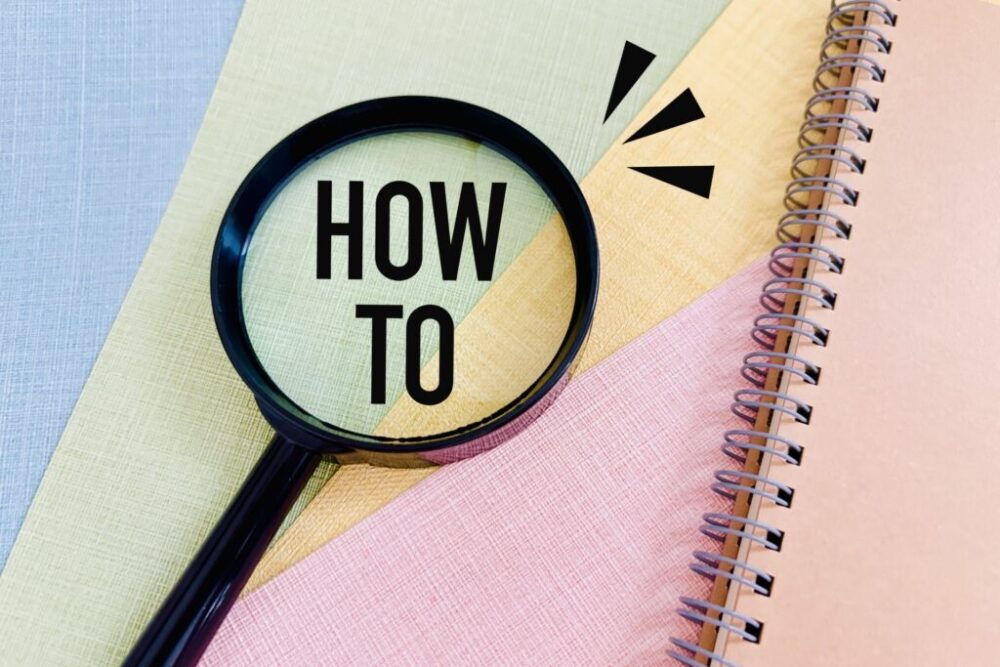
本を効率的に管理し利用者の利便性を高めるためには、さまざまな分類方法があります。主な分類方法は、以下のとおりです。
- 日本十進分類法
- Cコード
分類により、膨大な量の本を効率的に管理し、本を見つけやすくなります。
日本十進分類法
日本十進分類法は、図書館や書店で使われる資料分類法です。0〜9の10の主類に分けて本を整理します。3桁の数字で表現し、各主類は10の綱、各綱は10の目に細分化される点が特徴です。必要に応じて小数点以下でさらに細分化されます。913は日本の小説を表します。
日本十進分類法を使うと、本の内容を数字で簡単に表示可能です。日本十進分類法は1929年に制定され、現在は新訂10版(2014年)が最新となっています。国立国会図書館や公共図書館で広く採用されており、本を探すときに役立ちます。
日本十進分類法は図書以外の資料にも使え、幅広い情報を整理するときに便利です。分類記号と図書記号を組み合わせて請求記号を作成すると、本をすぐに見つけられます。
» 「日本十進分類法(NDC)新訂10版」|国立国会図書館(外部サイト)
Cコード
Cコードは、本の分類や管理に使われる4桁のコードです。出版社や書店が使用し、本の内容や特徴を簡潔に表します。Cコードの構成は、以下のとおりです。
- 1桁目:内容(0〜9)
- 2桁目:発売形態(0〜7)
- 3桁目:読者対象(0〜8)
- 4桁目:発行形態(0〜8)
Cコードを使うと、本の内容や発売形態、対象読者、発行形態がすぐわかります。書店での陳列や在庫管理だけでなく、出版統計にも活用されている点が特徴です。Cコードは日本図書コードの一部として使用され、よく日本十進分類法と併用されます。
» 分類記号(Cコード)一覧|日本図書コード管理センター(外部サイト)
自分に合った本の種類の選び方

自分に合った本の種類を選ぶのは、読書を充実させるうえで重要です。選び方について解説します。
ジャンルやサイズでの選び方
ジャンルやサイズを考慮すると、自分の興味や目的に合った本を見つけられます。興味のあるジャンルを絞り込みましょう。読書の目的に応じて適切なジャンルを選ぶと、自分に合った内容の本を効率的に見つけられます。サイズ選びでは、以下の点を考慮してください。
- 持ち運びの頻度
- 読書環境
- 予算
- 保管スペース
- 視力や読書習慣
通勤のときに読む場合、文庫本や新書が便利です。自宅でじっくり読むときは、単行本を選びましょう。本の内容の深さに応じて、一般書や専門書のどちらを選ぶかどうかも重要です。気軽に読みたい場合は文庫本や新書、長期保存したい場合は上製本を選ぶなど、目的に合わせて選んでください。
書店での選び方
書店で本を選ぶときは、以下の点を確認しましょう。
- 表紙や帯
- 内容の要約や著者情報が記載されているため、本の概要が把握できます。
- 目次
- 全体の構成の理解が可能です。
- 本文
- 数ページ読むと、文体や内容のレベルが合っているか確認できます。
- 出版社や発行年
- 情報の新しさや信頼性の判断に有効です。
- 著者の経歴や他の著作
- 専門性や信頼性を判断できます。
ページ数や装丁も重要です。本の読みやすさや持ち運びやすさも考慮しましょう。帯や裏表紙の推薦文や評価も参考になります。同じジャンルの他の本との比較検討も良い方法です。店員や他の客の意見も役立ちます。試し読みコーナーで読んでみる方法もおすすめです。
複数の方法を組み合わせると、自分に合った本を見つけやすくなります。
まとめ

本の種類の理解は、読書を豊かにするうえで重要です。さまざまなジャンルやサイズ、製本方法によって特徴が異なります。文芸や実用書、ビジネス書、絵本など、多くの種類の本があるため、自分の目的や好みに合わせて選びましょう。主なサイズは文庫本や新書、単行本の3種類です。
製本方法は上製本や並製本、クレスト装の3種類があります。日本十進分類法やCコードで分類されます。書店では本を手に取り、内容を確認しましょう。本の種類を知ると、読書がより充実します。自分に合った本を見つけ、読書の楽しみを広げてください。